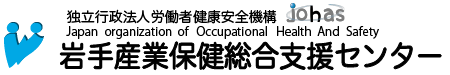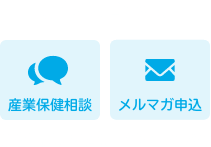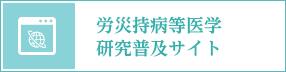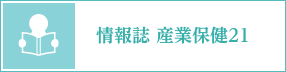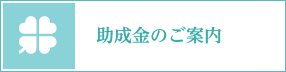〓〓★☆〓〓★☆〓〓★☆ ≪ コラム ≫ ☆★〓〓☆★〓〓☆★〓〓
◎ 今月のコラムは、4月発行「岩手産業保健総合支援センターだより」に掲載している当センター【産業保健相談員 立身 政信先生】のコラムをご紹介します!
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「社会的健康」
公益財団法人岩手県予防医学協会 産業保健支援部長 医学博士
産業保健相談員 立身政信
令和3年7月1日に発行された本誌46号のコラムで「健康とは…」という文章を載せたことがあります。「健康を求めていくことが既に健康な状態である。」という結論でしたが、その結びに「今回は個人的な健康について述べましたが、次の機会には社会的健康について考えてみたいと思います。」と書きました。
WHO憲章には「健康とは、肉体的にも精神的にも社会的にも完全に良い状態であり、云々」と書いていますが、肉体的健康と精神的健康は個人的な状態であり、健康診断でその評価をすることができる一方、社会的健康は集団の状態であり、個々人の健康情報を集計する「衛生統計」という手法で評価することができます。
「個人が社会の荒波にも負けずに生きていける状態」という人もいますが、それなら肉体的健康と精神的健康でどうにかいけそうな気がします。自然や文化を含めた人々の暮らす社会そのものが健康か否かということであり、個人的健康とは次元の違う概念であると私は捉えています。
「衛生統計」という言葉が出てきましたが、「衛生」とは明治時代に初代衛生局長の長与専斎がドイツ語のGesundheitspflegeを邦訳したもので、自伝の「松香私志」に中国の「荘子」を参照したことを書いています。
即ち「衛生」はGesundheitspflegeの直訳ではなく、長与専斎が「荘子」を参照して作り出した和製漢語なのです。松香私志には「字面高雅にして呼声も悪しからず」ということで「衛生」を採用したとしか記されていないのですが、長与専斎の心中には荘子の説く「衛生」の本来の意味が去来していたと考えられます。
「衛生」という言葉は社会的健康の考え方をとてもうまく表しているのです。
荘子第23編(庚桑楚篇)に、老子の言葉として「衛生とは能(よ)く一を抱くこと」とあります。老荘思想において「一」とは全てのことです。仏教が老荘思想の影響を受けて成立したとも言われる「禅」、その高僧であった内山興正老師は、「1=100/100、突き詰めれば全体/全体だ。」と喝破しました。前回「求道すでに道である」という言葉を引用させていただいた宮沢賢治の農民芸術概論綱要序文にも「新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある」という一節があります。私たちを含めて、地球上の生物は他の生物を摂取することで肉体を成長させ、やがてその肉体は微生物などに摂取されます。食物連鎖と呼ばれる循環です。動植物にとどまらず、大地も水もその循環の一部です。私たちが地球(或いは宇宙)という環境の中にいるのではなく、私たち自身が地球(宇宙)の一部、即ち地球(宇宙)そのものであるということです。社会的健康を人間の目線から捉えるならば、グローバルには生命のための理想的な地球環境を求めていくことであり、ローカルには文化的側面も含めた理想的な地域環境を求めていくことになるでしょう。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
- カテゴリ
- 月別
アーカイブ