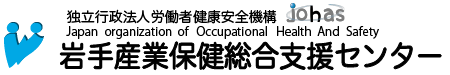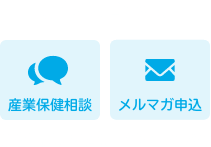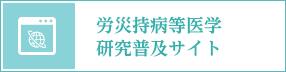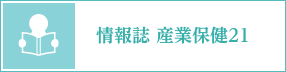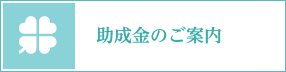〓〓★☆〓〓★☆〓〓★☆ ≪ コラム ≫ ☆★〓〓☆★〓〓☆★〓〓
◎ 今月のコラムは、7月発行「岩手産業保健総合支援センターだより」に掲載している当センター【産業保健相談員 上田 均先生】のコラムをご紹介します!
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
「最近増えている適応障害への対応 ~産業保健現場で求められる視点~」
産業保健相談員 上田 均(メンタルヘルス)
【もりおか心のクリニック 院長、認定産業医】
「異動して3か月ほど経ちますが、朝になると動けなくなってしまうんです」
──30代の男性社員Aさんは、異動先の上司と折り合いが悪く、毎朝出勤前に動悸と吐き気が出るようになりました。欠勤が続いた後に心療内科を受診し、適応障害と診断されました。Aさんのような事例は、現在、産業保健の現場でも珍しいものではなくなっています。
近年、職場におけるメンタルヘルス不調の中でも「適応障害」を訴えて精神科・心療内科を受診する方が増えています。相談対応や職場復帰支援の現場でも、適応障害は今や頻繁に取り上げられるテーマとなっており、産業保健に関わる私たちにとって理解と対応力が問われる疾患の一つです。
適応障害は、ある明確なストレス因子に対して情緒面や行動面に症状が現れる状態であり、診断基準上はその因子の出現から3か月以内に発症し、因子が解消されれば6か月以内に改善するとされています。職場においては、業務負荷、人間関係、役割や環境の変化などが代表的な誘因です。最近では、若年層に限らず中高年層でも発症が見られ、またテレワークや業務の複雑化に伴い、役割の曖昧さや孤立が新たなストレス因子として注目されています。
うつ病と症状が類似しており混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。共通点としては、抑うつ気分、不安、意欲低下、不眠、集中力の低下などのうつ症状が挙げられます。一方、適応障害は特定のストレス因子との因果関係が明瞭で、症状の重症度も比較的軽度で可逆的であるのに対し、うつ病では原因が特定できない場合も多く、病態は内因的で持続性・重症度が高い傾向にあります。特にうつ病では、強い自責感や希死念慮が見られることが多く、診断と介入のタイミングを誤らないことが重要です。
治療においては、適応障害ではストレス因子の回避または軽減を目的とした環境調整が中心となります。支持的精神療法や認知行動療法によるストレス対処スキルの獲得支援が有効です。うつ病治療では薬物療法が主体ですが、適応障害では薬物療法はあくまで補助的に用いられ、強い不安や抑うつ症状がある場合に限り、短期的に抗不安薬や抗うつ薬などが処方されます。
産業保健の立場から特に重要なのが、復職支援のプロセスです。段階的な勤務再開や業務内容の調整、上司・同僚の理解醸成が不可欠です。また、復職後も定期的な面談やモニタリングを通じて再燃を防ぐ体制の構築が求められます。なお、ストレス因子が職場環境に残存している場合には配置転換が必要となり、復職判断は慎重であるべきです。
適応障害は、対応次第で良好な経過をたどることが可能な疾患ですが、対応が遅れると慢性化やうつ病への移行リスクがあります。前述のように薬物療法は補助的であるため、医療機関のみでは対応が困難です。産業保健スタッフとして、本人への直接的な支援だけでなく、職場全体の理解促進、環境調整の提案、医療機関との橋渡しなど多面的な関わりが求められます。
━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━
- カテゴリ
- 月別
アーカイブ